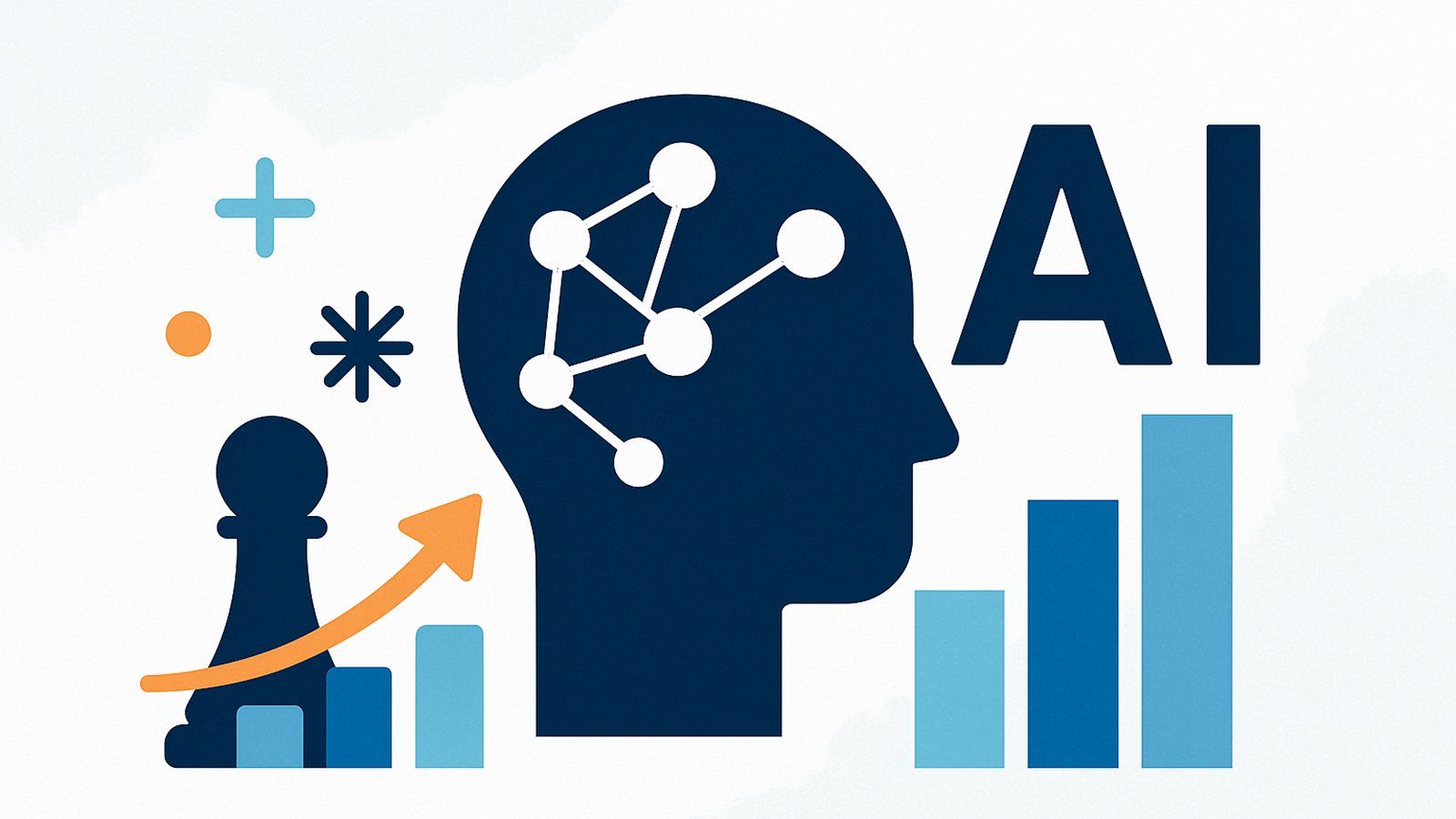【SHAPとは?】ISO 42001が求める「説明可能なAI」の実現手法―SHAP
ISO 42001とは
AIマネジメントシステム(AIMS)の概要と狙い
ISO/IEC 42001:2023 は、AI システムのライフサイクル全体を対象に “マネジメントシステム” を構築・運用するための要求事項を定めた世界初の国際規格です。発行は 2023 年 12 月で、現在は各国の認証スキーム整備が進んでいます。
| 中核テーマ | 目的 | 具体例 |
| 説明責任 | 出力結果に対し組織が責任を持つ | ログと根拠を残し、第三者監査に備える |
| 公平性 | バイアスの緩和・是正 | 属性ごとの誤差を定量評価 |
| 説明可能性 | 利害関係者が理解できる説明 | 個別予測レベルでの要因可視化 |
EU AI Act(2024 年 7 月公布、24 年 8 月発効)など各国規制とも連動しており、リスクが高い AI システムには “個別説明” を行う能力が強く求められます。
出典
ISO 42001が求める「説明可能性」とは
規格は、モデルの設計・学習・運用のあらゆる段階で「説明可能性」を確保し、結果をレビュー可能な形で保持する ことを要求します。本記事では実務で広く採用されているベストプラクティスとして、次の 3 層に分けて説明します。(※ 3 層構造は規格本文に直接書かれているわけではありません。)
- グローバル説明――モデル全体で重要な特徴量やルールを示す
- ローカル説明――個々の予測が下された理由を示す
- 運用説明――説明手法の妥当性・限界を文書化し、再学習や監査で再確認
SHAP は特に 2 と 3 を高精度かつ一貫性をもって実現できるため、ISO 42001 との親和性が高いと評価されています。
SHAPとは
ゲーム理論が支える説明可能 AI
SHAP は 2017 年に Lundberg & Lee が提案 した手法で、ゲーム理論の Shapley 値 を応用し「各特徴量が予測にどれだけ寄与したか」を数値で示します。
| 特徴 | 概要 |
| 一貫性 | モデルがある特徴量への依存度を高めれば SHAP 値も必ず増える |
| 局所性 | 1 件のデータに対しても厳密に寄与度を算定 |
| モデル非依存 | ツリー系・NN・大規模言語モデルなど多様なモデルで利用可 |
LIME など他の XAI 手法と比べ、説明の安定性 と 理論的保証 が強いため、規格や監査の現場で採用が拡大しています。
SHAPの種類
| SHAPバリアント | ニーズ | 目的 |
| TreeSHAP | 決定木系モデルで高速に正確に計算したい | 厳密な Shapley 値を効率的に計算 |
| FastTreeSHAP | より高速化したい | TreeSHAP をさらに高速化 |
| KernelSHAP | モデル内部にアクセスできない(ブラックボックス) | モデル非依存で近似計算 |
| DeepSHAP | ニューラルネットを使っている | 勾配を使って効率的に計算 |
| Text/Image SHAP | テキストや画像などの説明がしたい | マスク処理で可視化に対応 |
※SHAPバリアントとは、SHAP(SHapley Additive exPlanations)という説明可能AIの手法を、モデルの種類や用途に応じて最適化・拡張したアルゴリズムの“バリエーション(派生型)”のことを指します。
アルゴリズム別 SHAPの使い分け
| SHAPバリアント | 主な対応モデル | 特徴 | 推奨速度目安※ |
| TreeSHAP | 決定木系全般(勾配ブースティング, Random Forest, CatBoost など) | Shapley値を厳密に計算できる高速アルゴリズム | ★★★ |
| FastTreeSHAP | 上記と同じ | LinkedIn が開発。FastTreeSHAP v1: ~1.5×、v2: ~2.5× の高速化(単一コア比較) (LinkedIn) | ★★★★ |
| KernelSHAP | モデル非依存 | 近似計算(重み付け回帰でサンプリング)。ブラックボックス API でも可 | ★ |
| DeepSHAP | ニューラルネット | DeepLIFT をベースに勾配伝播で近似 Shapley 値 (Captum) | ★★ |
| Text / Image SHAP(PartitionExplainer 系) | NLP / CV | トークンやスーパー・ピクセル単位でマスクし寄与度を可視化。構造化マスカーで高速化 (SHAP) | ★★ |
※★が多いほど高速 用途ごとの早見表 ・大量バッチ推論 × 木モデル → Fast TreeSHAP ・ブラックボックスAPI → KernelSHAP ・生成AIやLLM → Text SHAPでトークンレベル寄与度
課題
SHAPには運用上の注意点もありますが、重要なのは課題を知った上でどのように活用するかという視点です。
これらを適切に管理すれば、ISO 42001が求める“説明可能性”の要件を十分に満たすことができます。
- 多重共線性
- 強く相関した特徴があると寄与度が分散し、解釈が難しくなる。
- 解決策:多重共線性の高い特徴を事前にまとめて Grouped SHAP を適用。
- 外挿解釈の危険
- SHAPは観測データ範囲外の挙動を保証しない。
- モデル外挙動を検証するシナリオテストが必須。
- 計算コスト
- 大規模データ・複雑モデルでは秒単位→分単位に。
- Tree系なら Fast TreeSHAP、深層学習ではサブサンプリング+キャッシュ戦略が有効。
- 参考: GitHub
- プライバシー
- SHAP値そのものが機微情報を推定できる場合がある。
- ロールベースアクセスと差分プライバシー加工が推奨。
導入時の留意点
SHAP だけでは完結しない
- 解釈コスト: 数値が正負どちらを示すか、必ず業務側とすり合わせる
- 複雑モデルの近似誤差: 大規模 Transformer などでは計算量・近似精度の検証が必須
- 倫理的判断の限界: “良い・悪い” の最終判断は人間と社内ポリシーが担う
- 多重共線性と特徴量依存: 強い相関がある特徴は寄与度が分散して誤解を招くため、Grouped SHAP やドメイン知識での特徴量まとめが必要
- データ/モデル・ドリフト対応: SHAP は学習時の分布を前提とするため、定期的にベースラインを更新しドリフト監視とセットで運用する
- プライバシー漏えいリスク: 個別 SHAP 値が機微情報を推定しうる。公開範囲をロールベースで制限し、必要に応じてノイズ付与(差分プライバシー)を検討する
これらを補完するため、責任体制・レビュー会議 を AIMS プロセスに明示し、SHAP を過信しない運用が推奨されます。
補完手法の例Counterfactual 解析や Causal SHAP を併用すると、バイアスの根因分析がより精緻になります。
まとめ表
ISO 42001 と SHAP の関係早見
| 観点 | ISO 42001 要求 | SHAP が提供する機能 |
| 個別説明 | 利害関係者が理解可能な根拠の提示 | 局所的 SHAP 値で数値+可視化 |
| 公平性 | バイアス検知と是正策の提示 | 属性別 SHAP 集計で影響度を定量化 |
| 継続的改善 | 再学習時の変化モニタリング | 時系列で SHAP 値を比較し逸脱を検出 |
| 監査証跡 | 判断根拠の保全・開示 | SHAP 出力をログ保存し再現性を確保 |
参考リンク
- ISO/IEC 42001 公式ページ:https://www.iso.org/standard/81230.html
- EU AI Act 採択と発効タイムライン:https://artificialintelligenceact.eu/developments
- Lundberg & Lee, “A Unified Approach to Interpreting Model Predictions” (SHAP 提案論文):https://arxiv.org/abs/1705.07874
- SHAP GitHub リポジトリ:https://github.com/slundberg/shap
- ISO 42001 発行ニュース(IAF Outlook):https://iaf.news/2024/05/31/iso-iec-42001-hype-or-a-guiding-light
- NIST AI Risk Management Framework 1.0(AI RMF)(米国 NIST, 2023-01):https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf
AI モデルの設計から AI導入まで、株式会社 Elcamy では幅広いサポートを提供しています。貴社の AI ガバナンス強化をご検討中であれば、ぜひご相談ください。